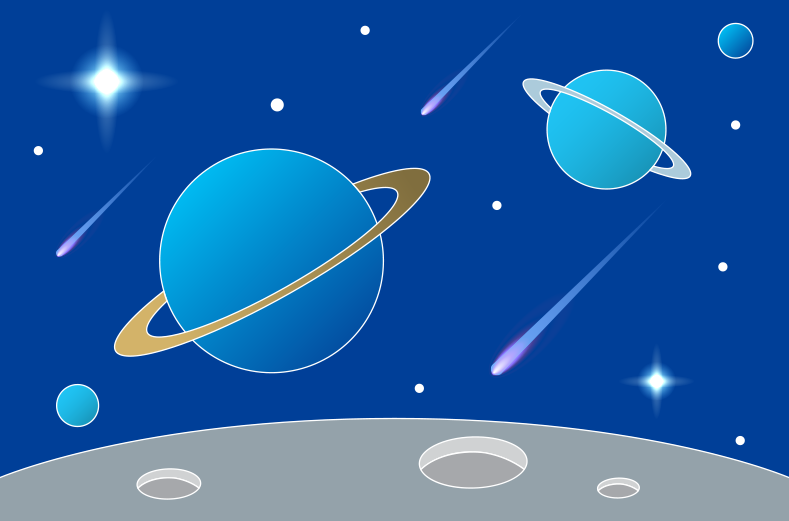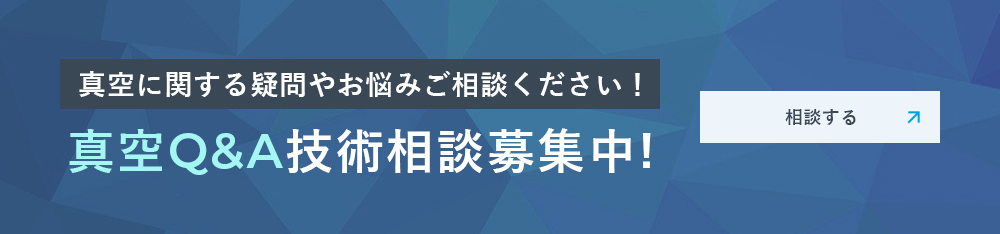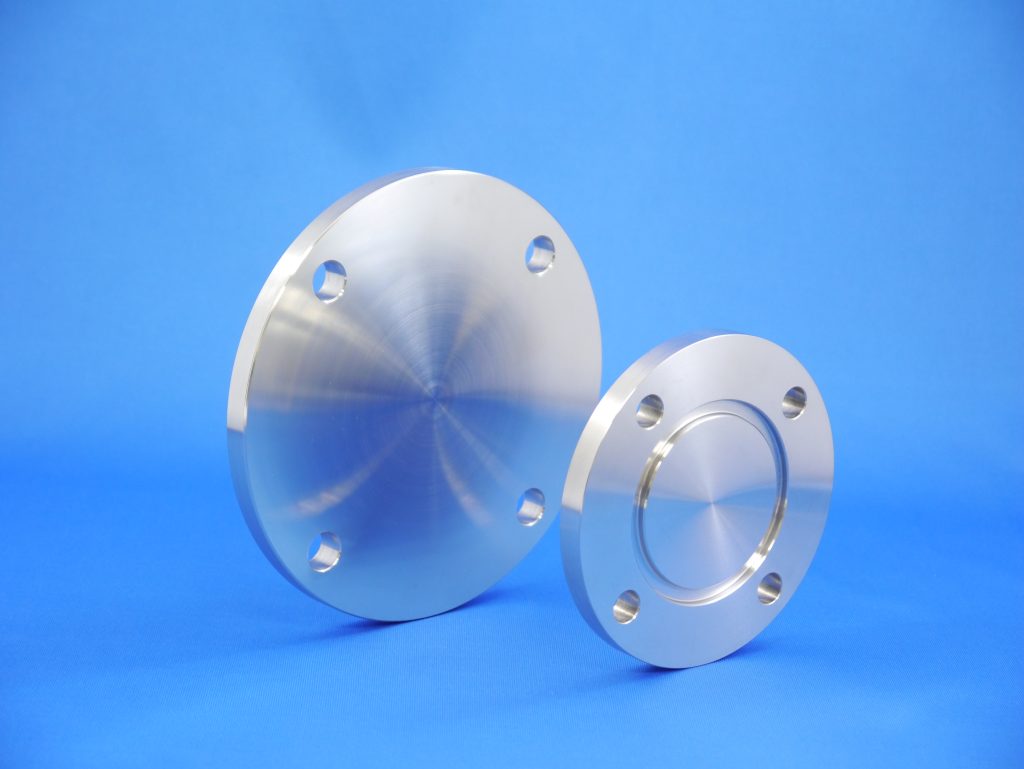Technical Guide
真空とは
簡単に言うと、気体分子が非常に少ない状態のことを指します。
産業分野で扱う真空は、完全に何もない空間(絶対真空)とは異なり、ある程度空気が薄くなった状態です。
日本産業規格(JIS)では「通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間の状態」と定義されています。
絶対真空とは
完全に何も無い、つまり、空間中に分子が一つもない真空状態をいいます。
現実の世界では絶対真空を作り出すことは不可能ですが、圧力の基準として用いられています。
気圧と真空度
地上では1気圧(1013hPa)ですが、真空ではこの圧力が極端に低くなります。
例えば、10-3Pa(パスカル)の環境では、1気圧に比べて1億分の1程度しか気体分子が存在しません。
真空の分類(低真空・高真空・超高真空)
日本産業規格(JIS)では圧力の範囲によって真空を5段階に分類しています。
| 真空度 | 圧力範囲 | 特徴・主な用途 |
|---|---|---|
| 低真空 | 大気圧~100Pa | 一般的な真空包装・吸着パッド |
| 中真空 | 10~10-1Pa | 真空乾燥・真空蒸留 |
| 高真空 | 10-1~10-5Pa | 半導体製造・蒸着装置 |
| 超高真空 | 10-5~10-9Pa | 研究開発・電子顕微鏡 |
| 極高真空 | 10-9Pa | 宇宙シミュレーション |
真空環境ならではの特性
沸点が下がる
真空中では、物質の沸点が下がります。
例えば、水が室温以下でも沸騰するため、真空乾燥やフリーズドライに使われています。
また、沸点の高い金属材料、例えばアルミは大気中では沸点が2500℃と非常に高温ですが、
真空中(10-5 Pa程度)では700℃程度まで下がるため、蒸着による成膜がしやすくなります。
熱が伝わりにくくなる
真空中は気体が薄く、対流や熱伝導がかなり小さくなるため、断熱効果があります。
ただし、熱放射は真空中でも伝わります。太陽の熱が地球まで伝わるのはこのためです。
化学変化や腐食が起きにくくなる
大気中では酸化などのさまざまな化学変化や、微生物による腐食などが起こりますが、
真空中では酸素などの気体が極端に少ないため、酸化や微生物の活動が起こりにくくなります。
電球のタングステンフィラメントは2000~3000℃に加熱されるため、
大気中ではすぐに酸化して切れてしまいますが、真空中に閉じ込めることで長時間発光することが可能です。
放電が起きやすくなる
大気中では雷くらいの高い電圧がないと放電は起きませんが、
ある程度の真空に圧力を調整すると電子が伝達しやすくなり、低い電圧でも放電が起こります。
真空を利用した身近な例
ストローで飲み物を吸うストローで飲み物を吸うとき、口の中の圧力を下げることで、 大気圧によってジュースが押し上げられる仕組みです。 |
 |
魔法瓶魔法瓶は、外壁と内壁の間を真空にして、空気による熱伝導を防ぐことで、 保温・保冷性能を高めています。 |
 |
真空パックレトルト食品やお肉の真空パックは、中の空気を抜いて、酸化や腐敗を防ぐ仕組みです。 |
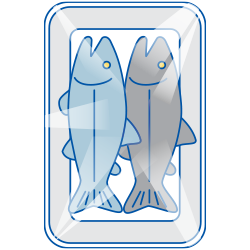 |
蛍光灯蛍光灯は、真空放電により管内に封入された水銀ガスが紫外線を出し、 内側に塗布された蛍光体が紫外線を可視光に変換する仕組みです。 |
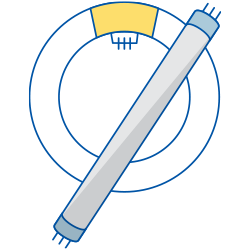 |
まとめ
-
真空とは、「気体分子が非常に少ない状態」であり、完全な無ではない。
-
圧力の低さによって真空度は5段階に分類され、用途によって使い分けられている。
-
真空には沸点の低下・熱の遮断・酸化の抑制・放電が起きやすいなどの特徴があり、様々な産業に応用されている。
-
私たちの身の回りにも、真空技術は広く使われており、意外と身近な存在である。
真空の仕組みや特性を知ることで、日常の技術や製造業の基盤を支えている重要性が見えてきます。
このページが真空について理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
あわせて読みたい
真空の力 – 真空の生み出す力について解説しています。
粘性流と分子流 – 真空中の気体の流れについて解説しています。
真空装置図鑑(カテゴリ) – 真空を用いた装置について解説しています。